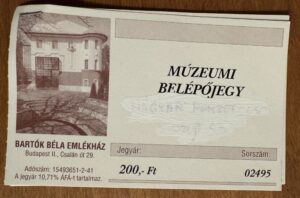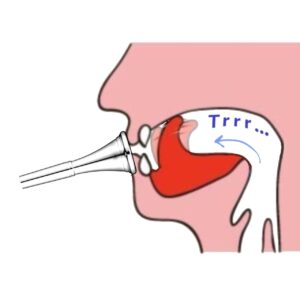2025.04.08
【夢に追いかぜコンサートin浜松のチケット】
4/6にアクトシティ友の会が発売していました。
4/12はいよいよ一般発売です。
ピアノの手がみえる左側のお席はけっこう売れているようです。
行こうと思っていた~という方は、お早めにご入手ください。
浜響98回定演まであと1週間程。
98回定期演奏会では、新たな試みとして開演前に前説を導入します🎤
前説を担当するのは、静岡県舞台芸術センター(通称スパック(SPAC))所属の俳優さんです!!
それでは、4/13日にお会いしましょう!!
チケット情報
2025.04.02
【♪50周年ロゴの愛称募集♪】
なんと!!4/13の定期演奏会では、50周年ロゴの愛称の投票を行います!!!当日、アクトシティ浜松大ホールロビーにて開催です。お好きな愛称を一つ選んでシールをぺったんと貼るだけです。どんな愛称が候補に挙がっているか…気になりますよね??ぜひ、投票しがてら演奏会をお楽しみください!(ん?逆かな?)
今
秋から冬にかけて、チェコの草 原の風に吹かれていた波小僧は 今、ルーマニアの大地にいた…いや、そんな訳はない今日はパート練習場所は三方原…日本じゃん。
「ルーマニア民族舞曲」は、その名の通り、ルーマニアのいわば民謡。7つの曲にはそれぞれ「~踊り」という題がついています。たとえば1曲目はJocul cu bâtă。訳すと「棒踊り」。bâtăって単語から、何となく想像できるけど、どうやって棒を持って踊るの?2曲目はPe loc?何?3曲めは?イメージが共有できなければ踊れないではないですかコミュニケーションの場であるパート練習ですから、みんなであれやこれやと話し合い。やっぱりこういう練習は、合奏とはまた一味違って楽しいや。
☆ パートトップ御愛用のこちらの鉛筆仕事でベルギーに行った時に買ったそうです。初めて見た時のインパクトはすごかった(笑)今日のパート練習でも大活躍のビッグ鉛筆でした。
写真提供:株式会社フォトGT 高橋五郎スタジオ Copyright 2017 Hamamatsu Symphony Orchestra. All Rights Reserved.